人生で大きなエピソードの1つとなるのが、家づくり。
大きな買い物なので、失敗は許されない、失敗したくありません。
『家づくり』と一括りで言っても、中身・必要とされる知識は多岐にわたります。住宅業界に従事している人でなければ、初めて見聞きする事ばかりで勉強づくしです。
私自身、家づくりの勉強をしている中で『どんな知識を学べば良いのか?』『どんな本を読んだら良いのか?』が分からず、多くの本を購読し、勉強しました。
多くの本を読んで勉強したことで、あらゆるリスクや考えられうるポイントを網羅しながら家づくりをすることができた為、現在住み始めて1年の我が家ですが、大満足しています。
この記事では、
- 『家づくりのいろは』について分かりやすい本が知りたい
- 『間取り』について参考になる本が知りたい
- 家づくりを始めたばかりで何から読んだら良いかわからない
- 家づくりの本はたくさんあって、どれが良いか決められない
と言った方に、家づくりを終えたBekoが、実際に役立った本を厳選してご紹介します。
どうぞお付き合いください。
家づくりの本は読む順番が大事
冒頭でも述べましたが、家づくりに必要な知識は本当に多岐にわたります。例えば、
- 家づくりの流れ
- ローン
- 土地
- ハウスメーカー
- 間取り
- 家の構造
- 建材について
- 図面の読み方
- 工事の流れ
- 法律関係
等です。1番目立つ、人気のカテゴリは『間取り』だと思いますが、最初から『間取り』だけに特化した本を読むのは危険だと思います!
間取りの勉強は楽しく、情報もあふれているので目に留まりやすいのですが、そのほかの部分は、専門的な言葉が並んでくる為、後回しにしやすいです。しかし、いざ住宅業界の方々と対峙したときに、より重要になってくる知識は楽しい部分ではなく、それ以外のちょっと後回しにしたい部分だったりします。
まず最初に全体像をつかんでから、それぞれの項目を掘り下げていったほうが勉強しやすく知識も入りやすいのでおすすめです☆彡
『家づくりのいろは』1番最初に読むことをおすすめしたい本
![]()
![]()
![]()
こちらです!じゃんっ!
絶対幸せになる!家づくりの基本125
こちらの本は、毎年最新版が更新されており、現在2021年版が発売されています。我が家も当時の最新版にお世話になりました。
この本の魅力は、家づくりの最初に知っておくべき情報を、幅広くまとめてくれていることです。
家づくりはどのような流れで進むのか、家づくりとお金のこと、土地と法律のこと、間取りのことといった項目に加え、省エネ設備や快適な建材についての知識、さらには契約書や設計図の見方、工事の流れまでわかりやすくまとめてあります。
『本』と聞くと文字がつらつら…というのを想像しますが、こちらの本は図や絵を使いながら分かりやすく、内容はしっかり・見た目はポップに仕上げてくれているところも、専門用語が並び尻込みしやすい家づくり初心者目線に立ってくれていて、大変好感が持てます。
最初にこの本を読めば、ある程度の知識を頭に入れることができるので、まずはこの本から読み始めることをおすすめします!
『家づくりのいろは』おすすめの本②
![]()
![]()
![]()
こちらです!じゃんっ☆彡
誰も教えてくれない家づくりのすべて2020
この本の好きなところは、カバーがまずおしゃれであることです!
本を読み始める前に、カバーがおしゃれだとそれだけでも購読意欲がわきます。その点、この本は大合格!と言えると思います(^^)
しかし!この本をおすすめしたい真骨頂は見た目だけではありません。
家を建てる際に、『そもそも』の家づくりの流れって、皆さんご存じでしょうか。私自身も初めての事なので、右も左もわからない状態でのスタートでした。
この本は、『そもそもの家づくりのスケジュールは?』というところから、『各部屋ごとの間取りの考え方』までの基礎的な全体像を説明してくれているのが親切な本です。
恐らく、この本や、1冊目におすすめした本の知識がない状態で、住宅展示場に乗り込んでしまうと、『間取りはどんなのが良いですか?』とか、おしゃれで楽しい話題に先行され、肝心な部分をすっぽぬいて話を進めてしまっていたのではないかと思うとちょっと恐ろしいです。
さらに、この本の好きなところは、基本的な部分から、間取りについてまで、網羅した本になっていることです。
表題が『家づくりのすべて』なので、そりゃそうでしょ、というところですがw、お堅い大切な基本の部分から、キッチンやダイニング、トイレや収納まで、それぞれの間取りの考え方や工夫の仕方を細かく教えてくれます(^^)
また、『土地』に関する知識も得ることが出来るので、土地探しから始めるという方にもおすすめ出来る本です☆彡
『家づくりのいろは』おすすめの本③
ここまでは、割とポップで購読意欲を掻き立てられる2冊をご紹介してきましたが、ここで1冊、ちょっとアウトローな(笑)1冊をおすすめしたいと思います。
それがこちら!じゃんっ☆彡
絶対に後悔しないハウスメーカー&工務店選び
キャッチーな表題ではありますが、本の表紙は白と赤を基調とした、あまりおしゃれとは言えない雰囲気です。(すみません)
中身も白黒で進んでいくので、上の2冊と比較してしまうと、ちょっと読みづらさを感じる部分もあるかもしれません。
が!この本の何が良かったかと申しますと、
『不動産会社』や『ハウスメーカー』における我々顧客が注意しなければいけない視点が、私たち施主側に分かりやすく説明されていることです。
何でもそうだと思いますが、業界には業界の裏側というものがあって、その職種に属していなければ知ることのできない情報だったり仕組みというのは必ず存在すると思います。
『家を建てる』分野における住宅業界も多分に漏れず、『住宅業界ならではの仕組み』というのがあります。その仕組みの部分を、どちらかというと『注意喚起』的に教えてくれているのがこの本の特徴です。
この本に書いてあることが全てではないと思いますが、『きれいな世界』ではなく、『一視点』として、業界の仕組みを押さえておくことは、どのハウスメーカー・どの不動産を選ぶかという選択を迫られたときに、絶対に役立つ知識だと思います。
決してポップで明るい本ではないのですが(笑)、必要な知識・視点を得られる本として、おすすめさせていただきます。
『間取りについて』おすすめの本④
![]()
![]()
![]()
間取りを考える際に、私が最も役に立った本、それがこちら!
じゃんっ☆彡
間取りの方程式
『間取りの方程式』は、建築を学ぶ学生や若い設計者向けに書かれた本で、間取りを作るための住宅設計のいろはが説明されています。
こう説明すると、
『え!?ちょっと小難しい本なの?』
と尻込みしそうになりますが、中身は文字とイラストが1:1くらいのバランスで配分されていて、字体やイラストもポップでかわいらしく、専門的な話を分かりやすく説明してくれている本です。
ただ単に『キッチンはこう考えよう』とか、『リビングはこう考えよう』と言った、細切れの間取り本は数多く散見されますが、この本のすごいところは『間取りを考えていく順番』を1から順に説明してくれていることです。
駐車場・家の形状・日当たり・風通し・そして間取りそのもの。これらを順序だてて、こういう順番で考えていくというのが、建築を目指す方々向けに書かれているので、『本来の間取り』を考えるうえで必要な要素を漏れることなく網羅することが出来ます。
我々顧客側は、どうしても『広いリビング』『おしゃれな間取り』に目が行ってしまいがちですが、そこだけを見ていると、いざ家が建った時に『家が暗い』とか、『風通しが悪い』とか、『駐車場が狭い』とか、暮らすのに不便な要素が生まれて、後悔に繋がってしまうと思います。
基本的だけど漏れてはいけない間取りの知識を、ポップに分かりやすく学ぶことが出来るので、この本はとてもおすすめできる本です☆彡
『間取りについて』おすすめの本⑤
『間取りの方程式』が『間取りを考える際のいろは』的な位置づけの本ですが、もう1冊、間取りを考える際にお勧めしたい本がこちら!
じゃんっ☆彡
賢く建てるお金のかけ方・おさえ方
『間取りの方程式』は間取りを考える際の全体像を押さえていくような本なのですが、
この本は、素材の選び方や収納の考え方等、間取りに関わる『細かい部分』を具体的な寸法や写真を用いて説明してくれる、間取りを詳細に考えていく際に役立つ知識を押さえることのできる本です。
特に参考になったのは、『収納の考え方』についてです。収納を考えていく際の順序・物ごとに必要となる奥行の具体的な参考寸法は我が家でもまさに採用させていただきました(^^)
家が建ってから『あれ、これ入らない』とか、物に合わない奥行で使いづらかったりしないようにするには、まず『今所有しているものを把握する』ということはすごく大事で、我が家もやってよかったなと思っています(^^)どんなものをどのくらい持っているか、というのは、建築士さんにはわからないので、施主側がしっかり把握して自分たちに合った収納をカスタマイズすることが大切だということを学ばせていただいたと思います☆彡
写真やイラストも豊富で読みやすいので、ぜひおすすめしたい本です☆彡
まとめ
以上、実際におすすめできる本についてまとめてみました☆彡
- 家を建てる際には、『家づくりの全体像』を押さえられる本も必ず押さえるべき
- 住宅業界のルールや常識を知ることも大切
- 間取りの本は『間取り全体の考え方』を学ぶと、必要項目を漏れなく網羅できる
あくまで、いち素人のおすすめ本ではありますが、これから家を建てる方の少しでも参考になりましたら幸いです♪
とても長い記事になってしまいました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

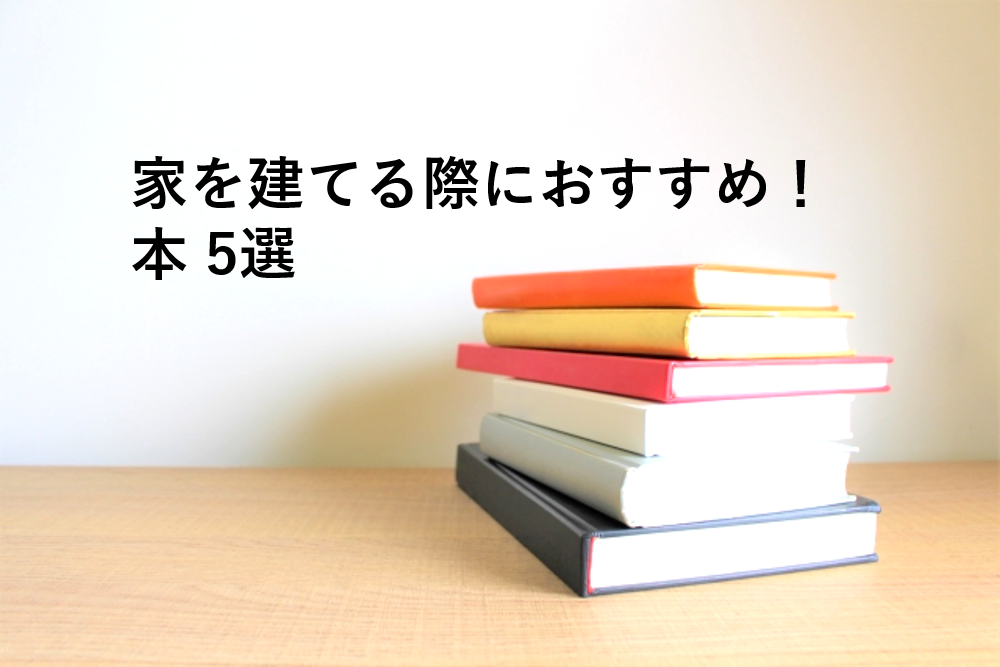








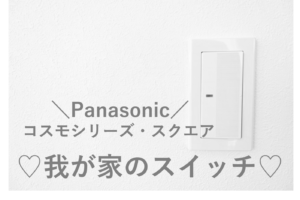





コメント